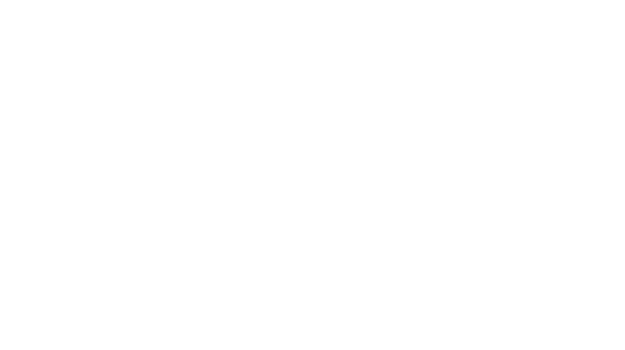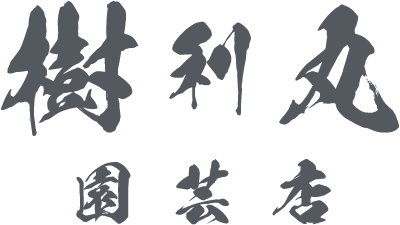ボンバックスの育て方|幹を丸くするためにやることを教えます
Share
こんにちは!
ボンバックスを育てていて、「元気がない」、「成長が思うように進まない…」 こんなお悩みはありませんか?
この記事では、ボンバックスを上手に育てるためのポイントや、よくあるトラブルの対処法をご紹介します。あなたのボンバックスを元気に育てるために、ぜひ参考にしてください!

目次
ボンバックスとは

ボンバックスは、中南米に自生し、グアテマラの国樹として知られています。正式名は「プセウドボンバックス」ですが、日本ではボンバックスの名で流通し、塊根植物として扱われています。幹の基部には緑色の筋が入り、成長していくと次第に筋がひび割れていきます。手のひらを広げたような葉は、冬になるとすべて落ちますが、春になると新芽が出てきます。
| 科 | アオイ科(Malvaceae) |
|---|---|
| 属 | プセウドボンバックス属(Pseudobombax) |
| 原産地 | 中南米 |
| 耐寒温度 | 10℃ |
| 耐陰性 | ややあり |
| 育てやすさ | 育てやすい |
ボンバックスの幹を丸くする強剪定のやり方

ボンバックスの幹は縦に伸びることが多いですが、毎年強剪定を行うことで幹を太くすることができます。幹が太くなることで、個性的な形と存在感が引き立ちます。
強剪定とは?
強剪定とは、太い枝を切りつめたり、相当な量の枝や葉を切ることで、植物の成長エネルギーを幹に集中させる方法です。一番太い主幹を切る場合は胴切りともいいます。
剪定時期
春(成長期)と、秋(休眠期に入る前)に行いましょう。真夏日や梅雨の湿度の高い日は、切り口が乾かず腐りやすくなるので避けます。新しい芽を出しやすく、剪定によるダメージからの回復が早い春に行うのが最適です。
剪定箇所
~枝分かれしてる場合~
過去に剪定した切り口から枝が出ている場合は、切り口に合わせて全ての枝を剪定します。

~枝分かれしてない場合~
切った下側が太くなっていくので、枝分かれがなく幹が一本の場合は、太くしたい高さの所で切ります。ハサミで切れない太さの場合は、カッターやナイフを使用するとよいでしょう。


剪定後の管理
葉剪定後は風通しが良く、直射日光を避けた明るい場所で管理します。切り口はやがて塞がり、新芽が出てきます。
切り口が大きいと、完全にふさがるには時間がかかります。その間に雑菌が侵入すると枯れてしまうこともあるので、融合材といわれる切り口を保護するものを塗ると、切り口を早く治すことができ、雑菌による枯れを防ぐことができます。切り口が直径2㎝以上のときに塗っておくと安心です。
~代表的な融合材~
種類により色や効果が違います。殺菌成分入りのものがおすすめです。
- トップジンMペースト:最も一般的で殺菌成分があるが、オレンジ色で目立つ
- バッチレート:殺菌成分あり、黄緑色
- キヨナール:殺菌成分あり、緑色
- カルスメイト:殺菌成分なし、茶褐色
~入手しやすい代替品~
融合材よりも安価なので、試しやすいです。
- 木工用ボンド:殺菌成分はないが、切り口を保護できる。水溶性のため、雨に当たると取れてしまう
- メネデール:植物の活性剤だが、切り口に被膜を作り保護してくれる
ボンバックスの育て方ハウツー

ボンバックスはどのように育てると良いのか、置き場や水やりの頻度、植え替えの時期など基本をご紹介します。注意点も記載していますのであわせてチェックしてください。
~ボンバックスの育て方のポイント~
- 年間を通して日当たりの良い場所に置く
- 丸くしたいなら水やりは控えめに
- 冬場の水やりは断水気味に
最適な置き場所は?
年間を通して冷暖房の風が直接当たらない、日当たりと風通しの良い場所に置くと良いです。暖かい時期は外での管理でも問題ありませんが、10℃を下回ったら室内に取り込み、10℃を下回らないようにします。葉が全て落ちても光合成をしているので、暗いところではなく明るい場所に置きましょう。
水やり頻度は?
春〜夏の生育期は、土が乾いたら鉢底から出るくらいたっぷりあげましょう。気温が下がる秋〜冬は、水やり頻度を減らして乾燥気味にします。土の中が乾いてから2〜3日後が目安です。
鉢皿にいつも水がたまっていたり土がいつも湿っていると、根腐れを起こし不調の原因となるため注意が必要です。
〜落葉後〜
葉を落とした後は、休眠期に入り水をあまり必要としないため、水やり頻度を徐々に減らし、断水気味で管理をしてください。
月に1〜2回、気温の高い昼間に少量与えます。目安は、夜には土が乾く程度で、霧吹きで表土を軽く湿らす程度でも構いません。気温の下がる夜に土が湿っていると、根腐れを起こしやすくなります。

肥料は必要?
なくても育ちますが、与えると根が良く育ち成長が早くなり、大きく育ちます。
真夏を避けた春〜秋に2カ月に1回の置き肥や、2週間に1回の液肥を与えるとすくすく育ちます。冬は休眠期のため与えないようにします。肥料の与えすぎは根を痛めるため、回数や時期は使用する肥料の規定を守りましょう。
植え替え方法
鉢底からたくさん根が出ていたり、水の染み込みが悪くなってきた時は植え替えが必要です。一回り大きな鉢に植え替えましょう。
〜植え替え時期〜
真夏日を避けた、春〜夏に行います。根がびっしり固まっていたらほぐし、枯れている根があれば取り除きます。
〜使用する土〜
水はけが良く、通気性のある土を好みます。自分で配合する場合は、赤玉土6:鹿沼土2:軽石2の配合か、多肉植物用の土を使用すると手軽です。
割りばしなどで根の隙間にも土がいきわたるようにし、植え替え後はたっぷり水を与え、風通しの良い日陰で様子を見てから元の場所に戻します。
~栽培カレンダー~

増やし方
春〜秋に「挿し木」で増やすことができます。鉢のサイズは挿す枝に対して大きすぎると過湿状態になるので、枝と鉢の余白が1〜5㎝前後を目安に選びましょう。
~方法1 切ってすぐ植える~
- 枝を10cmほど切り取り、葉が多い場合は枝先の葉を2〜3枚だけにし、大きな葉は半分に切る。剪定した枝が太くて長い場合は、10㎝前後に分割してもよい。このとき、上下がわからなくならないように気を付ける
- 切った枝先を、1~2時間水に浸けて給水する
湿らせた赤玉土や鹿沼土などの新しい土に、割りばしなどで穴を開けてから挿す

~方法2 発根させてから植える~
- 枝を10cmほど切り取り、枝先の葉を2~3枚だけにする
- 枝の1/3が水に浸かるように小さめの花瓶やコップなどに挿しておく
- 根が出てきたら植え替えの手順と同じように鉢に植える
どちらも、直射日光の当たらない風通しの良い明るい日陰で管理します。
ボンバックスが不調?原因と対処法

ボンバックスを生育する上で、起こりうるトラブルと対処法をご紹介します。
根腐れ
下記の内容が当てはまる場合、根腐れの可能性があります。
- 幹がぶよぶよしている
- 水をあげてるのに元気がない
- 土がなかなか乾かない
~根腐れの対処法~
土の環境を変える必要があるため、風通しの良いところに置き根の周辺の湿度を低くします。春〜夏なら植え替えをしてもよいでしょう。ボンバックスは丸くなった幹に水分を貯めているので、過湿にならないように気をつけます。水やりの際は土が乾燥しているか確かめ、季節に合った適切な水やりを心がけましょう。
日光不足
下記の内容が当てはまる場合、日光不足の可能性があります。
- 葉が全体的に黄色くなってきた
- 枝がひょろひょろしている
- 暗い場所に置いている
~日光不足の対処法~
ボンバックスは日光を好むので、明るい場所に移動させましょう。暗いところからいきなり日光が当たる場所に移動すると葉焼けをしたり、葉が落ちてしまうので避けます。急な環境の変化にならないように、徐々に慣らすようにしましょう。
害虫

下記の内容が当てはまる場合、カイガラムシが原因の可能性があります。
- 白の貝殻に覆われたような虫を見つける
- ロウの塊のようなものを見かける
- 白くてふわふわしたものが付いている
- 葉や幹がベタベタしている
カイガラムシは春〜秋に見かけることの多い「吸汁害虫」で植物の生育に悪影響を及ぼしたり、病気を引き起こしたりします。甘い汁を出すので、アリが寄ってくることもあります。ボンバックスも「花外蜜線」という器官があり、茎から甘い樹液を出すことがあります。


~害虫の対処法~
カイガラムシの成虫は硬い殻で覆われているため薬剤が効きにくいです。なので歯ブラシや手で取り除きましょう。葉や幹のベタベタは湿らせた布で拭いたり、水やりのついでに葉水も与え洗い流します。
ボンバックスを買う時のポイント
ポイント1 元気な株かどうか
- 幹がぐらつかず、はりのあるもの
- 葉の表裏をみて害虫の発生していないもの
ポイント2 好みの樹形のものを選ぶ
- 上に伸びる樹形が好みなら、基部を剪定していないもの
- 幹を太くしたいなら、基部が剪定されある程度太くなっているもの
自分好みのお気に入りを見つけて楽しみましょう。