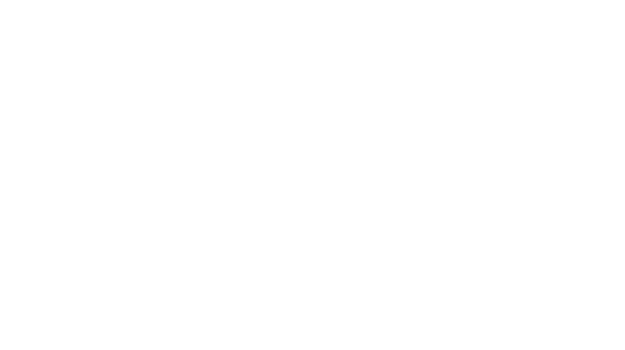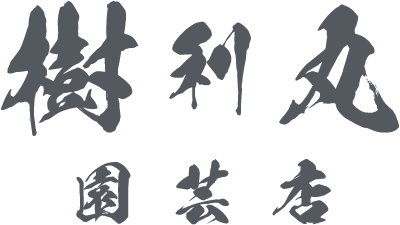初心者必見!エバーフレッシュの剪定&育て方のポイントを教えます
Share
こんにちは!
エバーフレッシュは、繊細な葉がふんわりと広がり涼やかな印象を与え、お部屋のアクセントにぴったりな観葉植物です。
初心者でも育てやすい植物ですが、元気に育てるためにはポイントがあるので、この記事ではエバーフレッシュの基本的な育て方から、よくあるトラブルとその対処法まで詳しく解説します。

目次
エバーフレッシュとは

エバーフレッシュは中南米原産の常緑高木で、日本にも自生するネムノキの仲間です。見た目はネムノキによく似ていますが、エバーフレッシュはネムノキのように落葉したり、淡紅色の花は咲かせません。「エバーフレッシュ」は流通名で正式名は「コヨバ・アルボレア」。小さな細長い葉が密につき、ふんわりとした姿のため、木が大きくなっても圧迫感なく優しい雰囲気を楽しめます。昼は葉を広げ、夜になると閉じるといった就眠(睡眠)運動をする珍しい習性があります。
| 科 | マメ科(Fabaceae) |
|---|---|
| 属 | コヨバ(コジョバ)属(Cojoba) |
| 原産地 | 中南米などの熱帯雨林地域 |
| 耐寒温度 | 5℃ |
| 耐陰性 | あり |
| 育てやすさ | 育てやすい |
| 花言葉 | 歓喜・胸のときめき |
エバーフレッシュの剪定の仕方
樹形を整えたり、風通しの改善のために定期的に剪定が必要です。春〜夏にかけて成長が活発な時期に行います。新芽は、付いていた葉と同じ方向に伸びます。理想の樹形が決まれば、伸ばしたい方向についている芽を残しましょう。
①樹形を整えるための剪定
まずはどんな樹形にしたいかイメージしましょう。一般的に、上の方にボリュームがある「逆三角形」にすると、美しく素敵になると言われています。
【切りたい場所に近い葉の上で切る】
縦・横に広がっている枝を抑え、樹形を整える剪定で、葉の上の新芽を残して切ります。新芽の色は茶色いですが、枯れているわけではないので安心してください。剪定後、残した新芽が伸びていきます。

②風通しの改善、今後の成長のための剪定
【枝の付け根から切る】
風通しをよくしたり今後の成長のために行う剪定で、樹形が美しくとも不要な枝は剪定します。枝の途中から切ると切った付近から新芽が出てしまうので、、枝の付け根から切り落とします。
~不要な枝の特徴~
- 徒長枝
- 他の枝と違い上に向かって勢いよく伸びる枝
- 交差枝
- 枝同士が重なり交差している枝
- 平行枝
- 他の枝と平行に伸びる枝
- 逆さ枝
- 内側に向かって伸びる枝
- 下がり枝
- 下に向かって伸びる枝
- 枯れている枝

エバーフレッシュの育て方ハウツー

エバーフレッシュはどのように育てると良いのか、置き場や水やりの頻度、植え替えの時期など基本をご紹介します。注意点も記載していますのであわせてチェックしてください。
~エバーフレッシュの育て方のポイント~
- 春から秋は水切れに注意する
- 寒さに弱いので冬は室内の暖かい場所に置く
- 年中霧吹きで葉水をする
最適な置き場所は?
日陰でも育ちますが日光を好むため、窓越しに日光が当たる場所に置くと良いです。5〜10月は外での管理も問題ありません。ただし夏の直射日光は葉焼けの原因になるので避けます。暑さには強いですが寒さは苦手なので、寒い時期は室内で管理し、10℃を下回らないようにします。
水やり頻度は?
春〜秋の生育期は、土の表面が乾いたら鉢底から出るくらいたっぷりあげましょう。気温の下がる冬は水やり頻度を減らし、中まで乾いてから与えます。表面が乾いてから2〜3日後が目安です。
鉢皿にいつも水がたまっていたり土がいつも湿っていると、根腐れを起こし不調の原因となるため注意が必要です。
葉から多くの水分を蒸散するため空気の乾燥に弱いので、年間を通してこまめに霧吹きで葉水をしましょう。

肥料は必要?
なくても育ちますが、葉数が多いので肥料を好みます。幹を太くしたい場合や、大きく育てたい場合は与えます。 真夏を避けた春〜秋に2カ月に1回の置き肥や、2週間に1回の液肥を与えるとすくすく育ちます。冬は休眠期のため与えないようにします。肥料の与えすぎは根を痛めるため、回数や時期は使用する肥料の規定を守りましょう。
植え替え方法
鉢底から根が出ていたり、水の染み込みが悪くなってきた時は植え替えが必要です。
根が乾燥しないように手早く一回り大きな鉢に植え替えましょう。
〜植え替え時期〜
真夏日を避けた、春〜夏に行います。根がびっしり固まっていたらほぐしましょう。
〜使用する土〜
水はけが良く、通気性のある土を好みます。草花用の土でも構いませんが、コバエが心配な方は「赤玉土」や「ピートモス」に「パーライト」を2割りほど混ぜるか、観葉植物用の土を使用すると手軽です。
割りばしなどで根の隙間にも土がいきわたるようにし、植え替え後はたっぷり水を与え、風通しの良い日陰で1日様子を見てから元の場所に戻します。根をほぐしたり切った場合は葉数を減らし、根に負担がかからないようにします。
〜栽培カレンダー〜

挿し木のやり方
春〜夏に挿し木で増やすことができます。使用する枝は生命力のある若い枝がよく、梅雨の時期が一番根が出やすいと言われています。剪定で切った枝を使用してもいいでしょう。鉢のサイズは挿す枝に対して大きすぎると過湿状態になるので、3号くらいの小さめを用意し、風通しの良い日陰で管理します。
~方法1 切ってすぐ植える~
- 健康な枝を10cmほど切り取り、枝先の葉を2~3枚残し葉を半分に切る
- 切った枝を1〜2時間水に挿して給水する
- 土に割りばしなどで穴を開けてから、新しい土(観葉植物用・赤玉土・バーミキュライトのいずれか)に挿す

~挿し木方法2 発根させてから植える~
- 健康な枝を10cmほど切り取り、枝先の葉を2~3枚残し葉を半分に切る
- 枝の1/3が水に浸かるように小さめの花瓶やコップなどに挿しておく
- 根が出てきたら植え替えの手順と同じように鉢に植える
根が出てきた後も土に植えず、水耕栽培することもできます。根腐れしないように水はできるだけこまめに交換しましょう。
花が咲いたら種で増やすこともできる!
春〜夏に、丸くて可愛らしい黄色〜黄緑色の綿毛のような花を咲かせます。花を咲かせたあとにらせん状にねじれた赤色のサヤをつけ、サヤが熟すと中から黒い種が出てきます。この種を播いて苗を増やします。作業適期は春〜夏です。
~種まきの手順~
- 種は洗ってぬめりをとっておく
- 2〜3号鉢に新しい土(観葉植物用・赤玉土・バーミキュライトのいずれか)を入れ、土を湿らせておく
- 種の大きさ分の穴をあけてから種を植え、土をかぶせる
- 再度たっぷり水を与え、風通しの良い日陰で管理する
エバーフレッシュが不調?原因と対処法
エバーフレッシュを生育する上で、起こりうるトラブルと対処法をご紹介します。
水分不足
下記の内容が当てはまる場合、水分不足の可能性があります。
- 葉に張りがなく下葉が垂れてきた
- 葉が落ちる
- 全体的にぐったりしている
- 昼間なのに葉が開かない
- 葉がぱりぱりになっている
エバーフレッシュが暗くなると葉を閉じるのは、葉から水分が蒸発するのを防ぐためです。昼間でも葉が開かないのは、水分の蒸発を抑えたい=水分が足りていないからです。
~水分不足の対処法~
エバーフレッシュは細かい葉が密についているので、水をたくさん欲しがります。寒い時期以外は水切れしないように適切な水やりを心がけましょう。
全体的に葉が黄色くなっていたり、ぱりぱりになっている場合は、思い切って葉を全部切り丸坊主にする手もあります。その際は、一つの枝に対し新芽を1〜2個残して切ります。
根腐れ
下記の内容が当てはまる場合、根腐れの可能性があります。
- 水をあげてるのに元気がない
- 土の表面にカビが生えている
- 全体気にぐったりしている
- 昼間なのに葉が開かない
~根腐れの対処法~
土の環境を変える必要があるため、風通しの良いところに置き根の周辺の湿度を低くします。春〜夏なら植え替えをしてもよいでしょう。
日光不足
下記の内容が当てはまる場合、日光不足の可能性があります。
- 葉が黄色くなってきた
- 枝がひょろひょろしている
- 暗い場所に置いている
~日光不足の対処法~
明るい場所に移動させましょう。暗いところからいきなり日光が当たる場所に移動すると葉焼けをしたり、葉が落ちてしまうので避けます。急な環境の変化にならないように、徐々に慣らすようにしましょう。
害虫
下記の内容が当てはまる場合、カイガラムシの可能性があります。
- 白の貝殻に覆われたような虫を見つける
- ロウの塊のようなものを見かける
- 葉や幹がベタベタしている
- アリをよくみかける
春〜秋に見かけることの多い「吸汁害虫」で植物の生育に悪影響を及ぼしたり、病気を引き起こしたりする害虫です。甘い汁を出すためアリが寄ってきます。エバーフレッシュ自体も「花外蜜腺」という器官があり、葉裏や幹から甘い樹液を出すことがあります。
~害虫の対処法~
カイガラムシの成虫は硬い殻で覆われているため薬剤が効きにくいです。なので歯ブラシや手で取り除きましょう。葉や幹のベタベタは湿らせた布で拭いたり、水やりのついでに葉水をし洗い流します。
エバーフレッシュを買う時のポイント
ポイント1 元気な株かどうか
- 幹が太く、多くの葉がついているもの
- 葉が変色しておらず、葉の密度が高いもの
- 葉の表裏をみて害虫の発生していないもの
ポイント2 鉢の大きさ
- 置く場所のスペースにあった大きさの鉢を選ぶ
- 成長して大きくなることを考える
エバーフレッシュは横よりも上に成長していくので、それを見越した上で置き場などを検討しましょう。